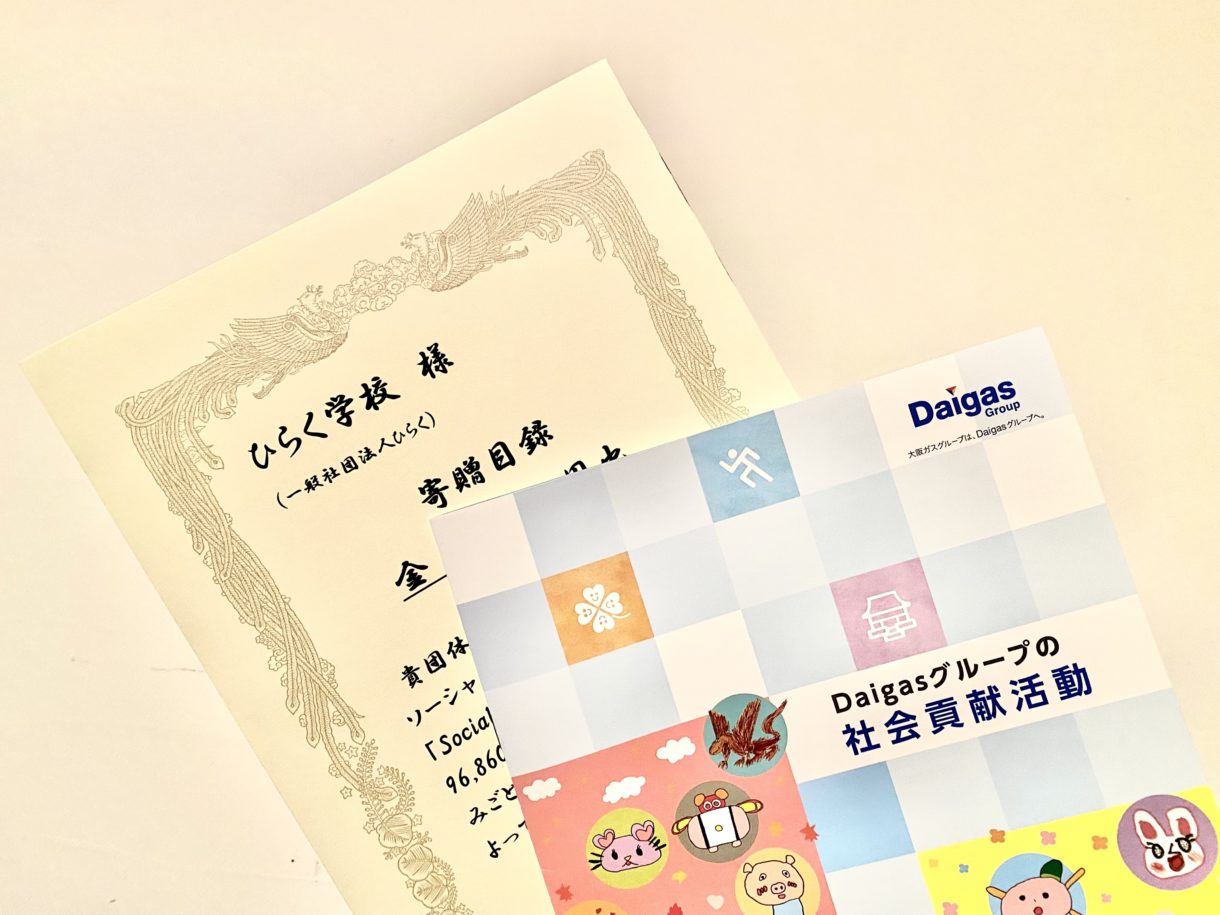「米粉への想い」を掲載いただきました。
- 2024.7.19.金曜
- お知らせ

生駒で有名な子どもの居場所の「南チロル堂」。
7月のかわらばんに米粉の特集をと取材をしていただきました。
昨年1500キロのお米の寄付をいただいたことから、たどり着いた『米粉』でした。
稲作の後継者問題で、耕作放棄地がだんだん増えだし、森に帰ろうとしている生駒市の稲作問題。田園をなんとか次の世代にもその光景を持続可能な形で引き継ぐことができないものかとみんなで意見を出し合った中で、何にでも形を変えることができると可能性を感じた「米粉」。チヂミやお好み焼き、肉まんや、お焼きなどのおかずにもなり、またクッキーやシフォンケーキなどお菓子にも使える優れものです。
グルテンフリーなので、アレルギーの方も安心して食べれて、カラダにすーっと馴染む優しい味が魅力です。
米粉は、今やいろんな大手カフェなどでも商品化されだし、どこででも見かけるようになってきました。農水省も昨年から推進活動に力を入れだし、レシピ集など、いろんな情報がわかりやすく配信されているのが、
こちら→ 米粉タイムズ
生駒市の高山町は、透明感のある水が流れる里山。そこで育った、ヒノヒカリ100%のひらく米粉。農業の後継者不足問題、そして、米粉商品のラベルは、一枚ずつ手作りで学生が作るあたたかい品物になっています。
生駒市のふるさと納税の返礼品としても掲載されていますので、農業とこれからの田園風景維持に、ぜひ皆様のお力をお借りできたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ふるさと納税こちらです。↓